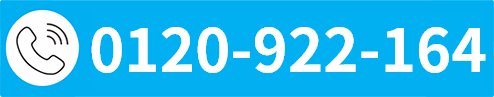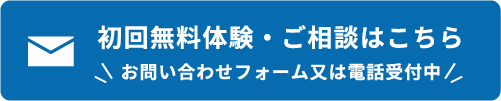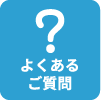脳卒中後の後遺症(私は、痺れ感と血行障害が強いです)について、マッサージに適さない部位、方法があれば、教えてください。|訪問マッサージ質問相談回答
2022.03.26
訪問マッサージに関してい頂いた質問に回答いたします。
質問:脳卒中後の後遺症(私は、痺れ感と血行障害が強いです)について、マッサージに適さない部位、方法があれば、教えてください。
ご質問
リハビリに詳しいと思われる方からの助言では脳卒中後のリハビリで、マッサージはお勧めしない、なぜなら、痺れ感の主な原因は、脳の認識と身体の動きの不一致からくる、脳のストレスのようなもので、マッサージは逆効果になるおそれがある、とまで言われていますが、脳卒中後の後遺症(私は、痺れ感と血行障害が強いです)について、マッサージに適さない部位、方法があれば、教えてください。
回答
痺れ感の原因が脳卒中によるものである場合、痺れ感の改善にマッサージがあまり効果的でないケースもあります。
例えば腕の痺れがあって、その原因が腕の筋肉(軟部組織なども含む)が悪く、腕を通る神経に緊張圧迫を与えている場合は、マッサージによって腕の筋肉の状態をよくすることで痺れが軽減がされやすいですが、脳卒中による脳のダメージが原因の痺れ感はマッサージによって筋肉の状態を良くしたとしてもあまり効果的でない可能性もあります。
ただし『マッサージは逆効果』とまでは言い切れないです。実際にマッサージ施術によって軽減される方もいますので、脳ダメージの損傷の程度や状態により異なり、一概に画一的にこれが良い・悪いと断定できていないのが現状(脳卒中ガイドライン)です。
特別、マッサージに適さない部位、方法はありません。。
血行障害については、脳卒中による脳のダメージが原因であったとしても、マッサージによりマッサージ施術した部位に血流改善が見込めますので、(根本的な改善ではないですが対症的な意味で)効果があると考えられます。
以上、回答となります。
回答者:藤和マッサージ代表 須藤新